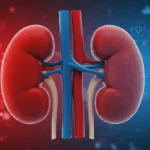まず初めに、これから「慢性腎臓病(CKD)」について、全6回にわたって調査結果をご報告いたします。
ただし、この内容はあくまで私個人の能力で調べたものですので、もしかしたら情報に間違いがあるかもしれません。したがって、もしこの記事を読んでCKDに興味がわいたり、ご自身の健康が気になったりした方は、ぜひご自身でさらに詳しくお調べになるか、あるいは病院を受診して専門医から直接説明を受けていただくことを強くお勧めします。
さて、私がなぜ今回このテーマについて調べようと思ったのか。その理由としましては、私自身が長年メタボ体型であり、そして今までの健康診断では毎回何かしらの指摘を受けていたという経緯があります。とはいえ、若い頃は「まだ大丈夫だろう」と、その結果をあまり気にしないで生きてきました。
ところが、50歳という節目を過ぎたことで、やはり自分の健康について真剣に考えるようになりました。そこで、これを機に自分の体を見つめ直そうと決心し、今回の調査に至ったというわけです。
以上の経験から、私自身の反省も込めて、皆様には「早期発見・早期対応」がいかに大切かをお伝えしたく、このように筆をとった次第です。
第1章 慢性腎臓病と加齢による腎臓の変化への序論
CKDの定義:「沈黙の病」が数百万人に影響
慢性腎臓病(CKD)は、腎臓の働きが長期間にわたって少しずつ低下していく病気です。初期の段階では自覚症状がほとんどなく、「沈黙の病」と呼ばれることもあります。日本だけでも数百万人がこの病気に影響を受けているといわれています。気づかないまま進行すると、透析や腎移植が必要になる場合もあります。
ここでイメージしやすい例をあげると、腎臓は体の「フィルター」のような役割を果たしています。ちょうど空気清浄機や水道の浄水器のフィルターが汚れると性能が落ちるのと同じように、腎臓も徐々に疲れていくのです。
なぜ年齢が重要なのか:45歳以降の腎機能の自然的変化
人は年齢を重ねるとともに、体のさまざまな機能が少しずつ低下していきます。腎臓も例外ではありません。特に45歳を過ぎると、腎臓のろ過能力(GFR)が自然に下がり始めます。これは老化の一部であり、すべてが病気というわけではありません。
腎臓を蛇口にたとえるとわかりやすいです。若いころは蛇口をひねれば勢いよく水が流れます。しかし年齢を重ねると、蛇口の中が少しずつ錆びてきて水の流れが弱まっていくように、腎臓の働きも少しずつ落ちていきます。ですから、中高年になったら「自然な変化」と「病気による変化」を区別することがとても重要です。
診断の二本柱:GFRとタンパク尿を理解する
CKDを診断するために特に重要な指標が2つあります。それが「GFR」と「タンパク尿」です。
GFR(糸球体ろ過量)
GFRとは、腎臓がどれくらい血液をきれいにできるかを表す数値です。さきほどの蛇口の例でいえば、「1分間にどれくらい水が出るか」を測るようなものです。水の量が少なくなれば、腎臓の働きが弱っているサインです。
タンパク尿
もうひとつの大切なサインが「タンパク尿」です。本来、腎臓はたんぱく質のような大きな成分は漏らさず体に残します。しかし腎臓が傷むと、ふるいの目が粗くなったようにたんぱく質が尿に漏れてしまいます。これは「フィルターの異常」を示す警告サインです。
この2つの指標を組み合わせて評価することで、腎臓の健康状態を詳しく知ることができます。GFRが低下しているか、タンパク尿が出ているかを定期的にチェックすることは、CKDの早期発見につながります。
まとめ
慢性腎臓病(CKD)は気づかないうちに進む「沈黙の病」であり、年齢とともに腎臓が自然に弱っていくこともあります。しかし、GFRやタンパク尿を定期的に確認すれば、腎臓の変化にいち早く気づくことができます。腎臓は「体のフィルター」であり、「蛇口」や「ふるい」に例えるとイメージしやすいでしょう。まずは腎臓の働きを理解することが、将来の健康を守る第一歩となります。