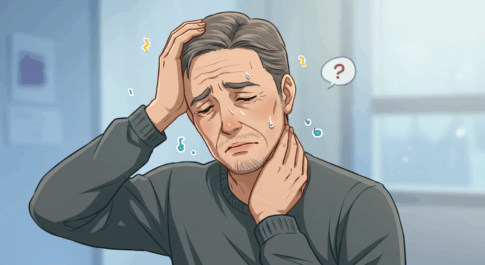高度順応はとても大切です。大弛峠の駐車場で仮眠して目指した金峰山。私の体調不良にて早期撤退した失敗談です。前日は夜勤明けで仮眠せず40時間以上寝ていない状態で晩御飯に中華料理をたらふく食べてお酒を飲んで助手席で揺られながら大弛峠駐車場に到着。標高2360m。3時間ほど仮眠して登る予定でしたが。就寝後しばらくしてめまい、頭痛、吐き気に襲われるが胃がもたれているのだろう。寝不足だったから頭が痛い。と耐えながら3時間後出発の準備をした私。体調は相変わらず最悪。でもせっかく来たし妻も一緒だし、ここで体調悪いからと断ったら妻に悪いしなんて考えでスタートしたのが間違いでした。
その眠気大丈夫?高度順応のサインと高山病の危険な兆候
登山中にふと襲ってくる眠気。「ちょっと疲れただけかな?」と軽く考えていませんか?実はその眠気、高所があなたの体に送る重要なメッセージかもしれません。
楽しいはずの登山が、一転して深刻な事態に陥ることも…。それは、単なる疲れからくる眠気と、命に関わる高山病の危険なサインである眠気を見分けられるかどうかにかかっています。
この記事では、なぜ高所で眠くなるのか、その眠気が安全なものか危険なものかを判断するための具体的なポイント、そして安全に登山を楽しむための予防策まで、わかりやすく解説していきます。あなたの次の登山を、より安全で楽しいものにするために、ぜひ最後までお読みください。

なぜ高所では眠くなるの?体の変化と睡眠の質
まず、なぜ高所では特有の眠気や体調の変化が起こるのでしょうか。
標高が2,500mを超えると、気圧が下がり、一回の呼吸で取り込める酸素の量が減ってしまいます。この「低酸素」状態に体を慣らそうとする働きが「高度順応」です。
体は、より多くの酸素を取り込もうと、呼吸を速くしたり、心拍数を増やしたりと、一生懸命がんばります。この順応プロセスは、体に大きな負担をかけるため、疲労感や眠気を感じやすくなるのです。

さらに、高所では睡眠の質も大きく変化します。寝ている間も体は酸素を必要とするため、呼吸が浅くなったり、数秒間呼吸が止まっては、ハッと息を再開する「周期的呼吸」という現象が起こりやすくなります。これでは熟睡できるはずもなく、夜中に何度も目が覚めてしまい、結果として日中に強い眠気を感じてしまうのです。
「昨夜あまり眠れなかったから、日中眠いのは当たり前か」と感じるかもしれませんが、ここが重要な分かれ道。これが順応過程の眠気なのか、それとも危険なサインなのか、慎重に見極める必要があります。
ただの疲れ?それとも危険なサイン?眠気の種類を見分ける
登山中の眠気は、大きく分けて「安全な眠気」と「危険な眠気」の2種類があります。この違いを理解することが、あなたの命を守ります。
安全な眠気
- 肉体的な疲労 登山という運動による、ごく自然な疲れです。休憩や食事、水分補給で回復します。
- 睡眠不足からくる眠気 夜間の周期的呼吸などで、睡眠の質が低下した結果です。意識ははっきりしており、会話も普通にできます。
危険な眠気(高山病のサイン)
高山病(AMS)や、さらに重症化した高地脳浮腫(HACE)の症状として現れる眠気は、全く性質が異なります。

- ひどい二日酔いのような頭痛を伴う
- 吐き気や食欲不振がある
- 声をかけられても反応が鈍い、ウトウトしている(傾眠)
- まっすぐ歩けない、ふらつく(運動失調)
- 会話がかみあわない、時間や場所がわからなくなる
これらの症状、特に「頭痛」と「まっすぐ歩けない」というサインを伴う眠気は、脳が腫れ始めている危険な状態(高地脳浮腫)を示唆しています。これは生命に関わる緊急事態であり、一刻の猶予もありません。

自分の体を客観的にチェックする二つの方法
高所では判断力が鈍りがちです。「自分は大丈夫」と思い込まず、客観的なツールを使って自分の状態をチェックしましょう。
- レイク・ルイーズ・スコア(LLS)で自己診断 これは、高山病の重症度を測るための国際的な自己診断ツールです。「頭痛」「吐き気」「疲労感」「めまい」の4項目を点数化し、合計点が3点以上だと高山病と判断します。定期的にチェックすることで、体調の変化に早く気づくことができます。
- パルスオキシメーターで血中酸素飽和度(SpO2)を測定 指先に挟むだけで、血液中の酸素量を数値で確認できる便利な機器です。
- 90%未満:体がかなりの低酸素ストレスを感じています。要注意。
- 85%未満:危険な状態です。高度を上げるのは中止しましょう。
- 80%未満:非常に危険です。すぐに下山を検討すべきレベルです。

自覚症状(LLS)と客観的な数値(SpO2)を組み合わせることで、より正確に自分の状態を把握できます。
高山病を予防する4つの鉄則
高山病は、なってから対処するのではなく、ならないように予防することが最も重要です。以下の4つの鉄則を守りましょう。

- ゆっくり登る これが最も大切な原則です。体が低酸素に慣れる時間を与えてあげましょう。「高く登り、低く眠る」を意識し、急激に高度を上げる「弾丸登山」は絶対に避けてください。登山口に着いたら、すぐに登り始めずに1〜2時間その場で過ごすだけでも効果的です。
- こまめに水分補給をする 脱水は高山病のリスクを高めます。喉が渇く前に、1日に3〜4リットルを目安にこまめに水分を摂りましょう。尿の色が薄い黄色を保てていれば、水分が足りているサインです。
- エネルギー補給を忘れずに 高所では炭水化物が効率の良いエネルギー源になります。消化の良いおにぎりやパン、エネルギーゼリーなどを少量ずつ頻繁に食べるのがおすすめです。満腹は呼吸を妨げるので、食べ過ぎには注意しましょう。
- アルコールと睡眠薬は厳禁 アルコールや睡眠薬は、呼吸を抑制する作用があり、高所では非常に危険です。絶対に摂取しないでください。
もし危険なサインが出たら?迷わず「下山」を!
予防策を講じても、高山病の症状が出てしまうことはあります。もし、「まっすぐ歩けない」「意識がもうろうとする」「話がかみあわなくなる」といった危険なサインが現れたら、取るべき行動は一つだけです。
ただちに下山してください。
これが、重度の高山病に対する唯一確実で、最も効果的な治療法です。天候などが理由ですぐに下山できない場合でも、絶対にそれ以上高度を上げてはいけません。仲間と協力し、ためらわずに救助を要請してください。
登山の成功は、山頂に立つことだけではありません。全員が無事に家に帰ることこそが、本当の成功です。あなたの知識と、時に引き返す勇気が、あなた自身と仲間の命を守ります。次の登山も、安全第一で楽しんでくださいね。
まとめ:今回の失敗
結局私は睡眠不足でたらふく食べて標高2360mの大弛峠駐車場で仮眠という設定に問題がありました。結果高山病を引き起こし無理して登ったため途中から冷汗や腹痛、倦怠感、眠気など症状が悪化し撤退となったわけです。
睡眠中は生理的に呼吸ドライブ(呼吸をしようとする力)が低下する。しかし、高所では十分な酸素を得るために、覚醒時以上に呼吸を維持する必要がある 。なので高所では眠いからとすぐ寝てはいけないのです。起きて高度順応する必要があります。
私みたいに食べすぎとお酒の飲みすぎも原因の一つです。満腹は横隔膜の動きを妨げ、すでにストレス下にある呼吸や消化にさらなる負担をかける 。アルコールは呼吸中枢を抑制する作用がある 。特に睡眠中は生理的に呼吸が浅くなるため、これらの物質の摂取は低酸素状態を深刻に悪化させる可能性があり、極めて危険である。
金峰山敗退の原因からたくさんのことを学び、安心安全登山を心掛けているつまけんでした!