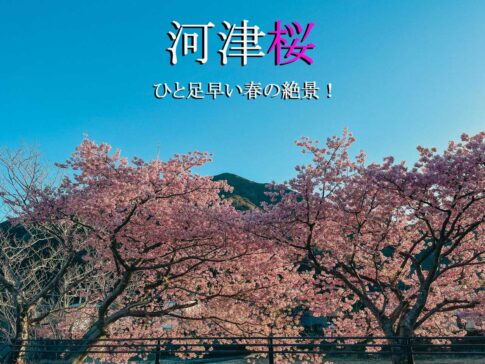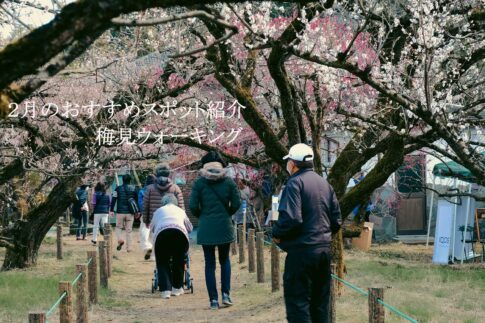なぜ「無趣味な妻」が問題になるのか
「無趣味な妻」という言葉は、テレビ番組やSNSでよく見かけます。たとえば、ドラマでは、趣味もなく家事だけをこなす妻が「退屈な存在」として描かれたり、ネットでは「趣味がない人とは会話が合わない」「つまらない人生を送っていそう」といった声があがることもあります。こうしたイメージは、「無趣味=ダメ」という社会の雰囲気を作り出しているといえるでしょう。
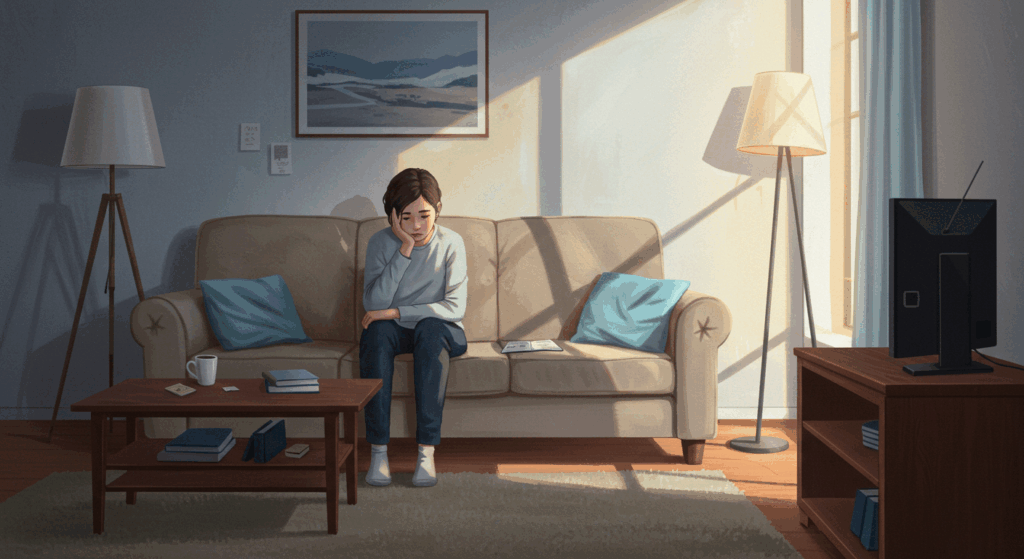
でも、趣味がないことを単純に「怠けている」「やる気がない」と決めつけてしまうのは、あまりにも一面的です。この記事では、「無趣味な妻」という現象を、個人の性格ややる気の問題としてではなく、性別による役割分担や社会の期待、家庭内の力関係など、広い視点から考えていきます。さらに、この状態が夫婦関係や家庭にどんな影響を与えるかについても見ていきます。
趣味を持てないのはなぜか:背景にある生活のリアル
まず、趣味を持てない理由のひとつに「時間がない」という現実的な問題があります。内閣府の2022年「男女共同参画白書」では、小さな子どもを持つ家庭では、女性の家事・育児時間が男性の約3倍にものぼると報告されています。特に夫婦間で家事や育児の分担が不公平だと、女性は「自分の時間」を持つのがとても難しくなります。この背景には、「母親は子どものために全てを捧げるべき」といった考えが、無意識のうちに影響していることもあるでしょう。
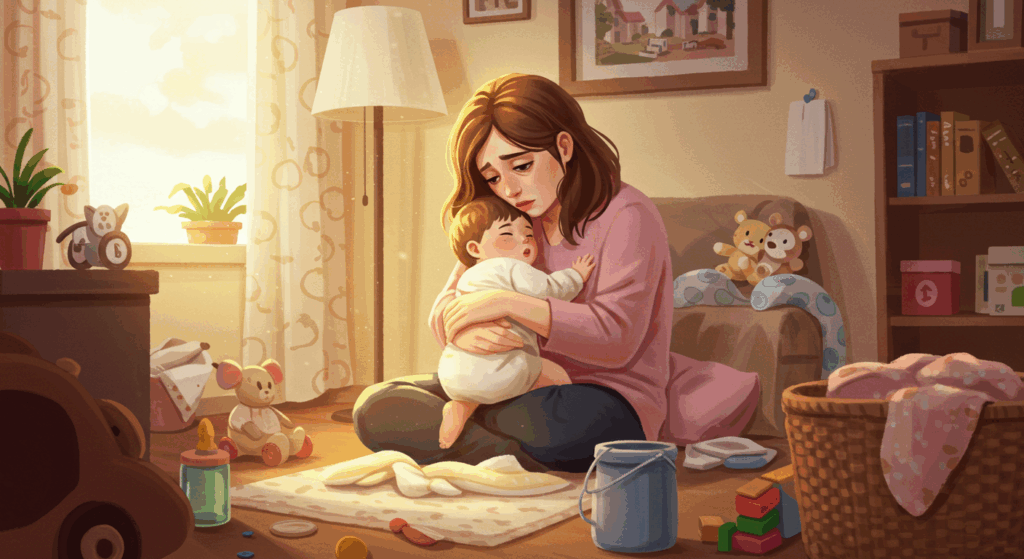
また、趣味を始めるには、ある程度の時間、お金、情報が必要です。こうしたリソースに恵まれていない人にとっては、そもそも趣味を見つけるチャンスが少ないのです。さらに、「どうせ続かない」「趣味は贅沢」といったネガティブな思い込みがあると、自分から趣味を始めようという気持ちも持ちづらくなります。これらは過去の失敗経験や他人との比較から生まれることが多く、無趣味の状態を長引かせる原因になります。
無趣味が夫婦関係に与える影響
趣味がないことが夫婦関係にどう影響するかというと、すぐに問題が起こるというよりも、少しずつ溝が広がっていくような形が多いです。たとえば、共通の話題がなくなれば会話の機会が減り、気持ちを共有する場も少なくなります。こうした静かな距離感の積み重ねが、心理的な孤立や疎外感につながることもあります。
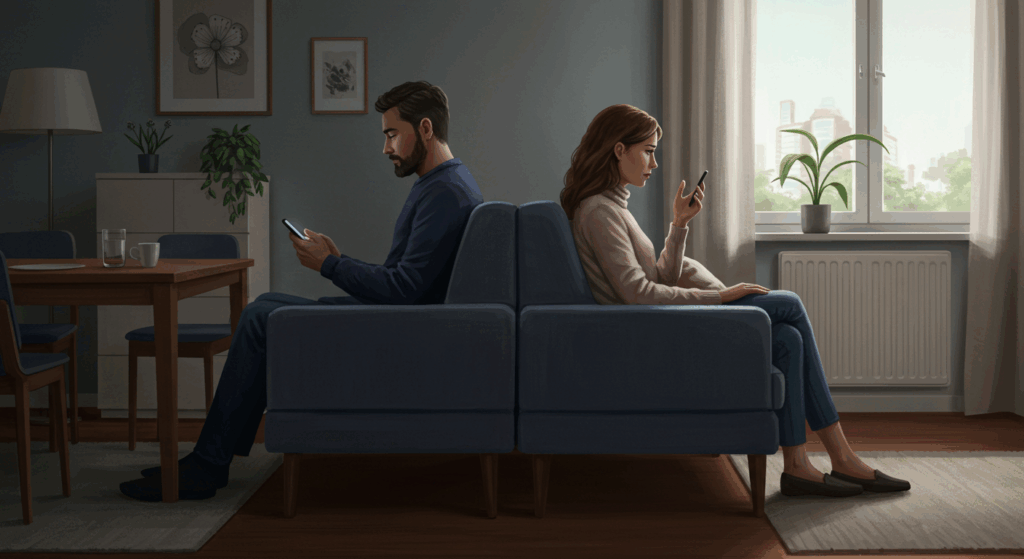
一方で、夫が趣味を通して自己実現したり、外の人とのつながりを持っている場合、その差が妻にとっては不公平に感じられることがあります。このような「ずれ」が長く続くと、夫婦の間でお互いを理解する力が弱まり、関係が冷えてしまう可能性もあります。
趣味を見つけるためのステップ
無趣味の状態から抜け出すには、まず自分をよく知ることが大切です。「自分は何に楽しさを感じるのか?」「どんな気持ちを満たしたいのか?」といったことを考えるところから始めます。そのためには、心理テスト(たとえば自己意識尺度や動機づけ尺度)や、自分のこれまでの人生を振り返るインタビューなどを活用すると、自分の興味や欲求が見えやすくなります。

たとえば、リラックスや気分転換を目的とするなら、読書、アロマ、日記、瞑想といった静かな活動が向いています。一方、創造的なことがしたい人には、刺繍、ガーデニング、料理、動画制作などの手作業がおすすめです。また、健康を意識するなら、ヨガや水中運動など、身体を使う趣味も良い選択肢です。
取り組みやすさを重視した導入法
趣味を始める最初のステップでは、プレッシャーの少ない形が効果的です。たとえば、一日体験講座や地域の公開教室、オンライン講座(YouTubeやUdemyなど)は、時間の拘束が少なく、自分のペースで試すことができます。
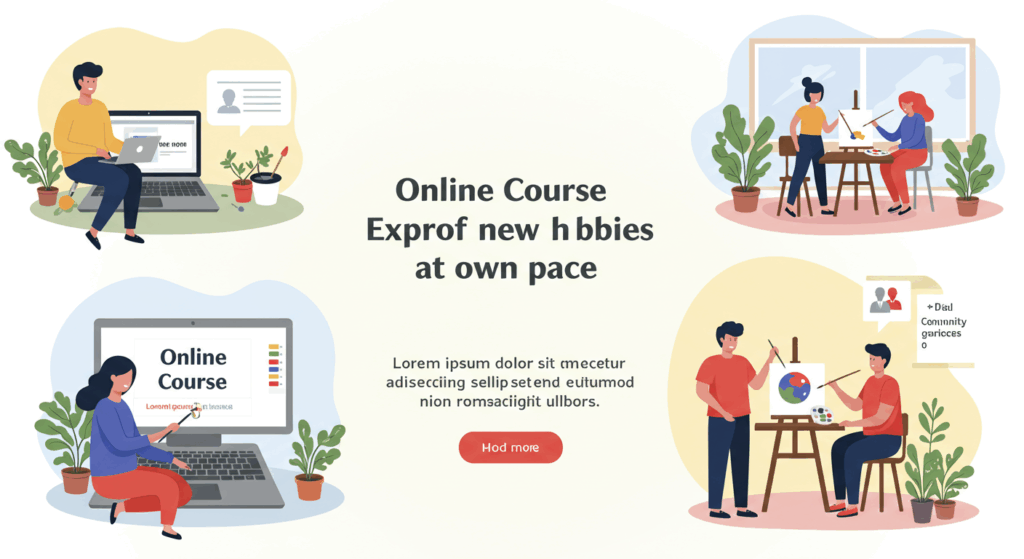
また、SNSなどで趣味を楽しんでいる人の投稿を見ることで、「自分にもできそう」と感じやすくなります。こうしたモデル(ロールモデル)を見ることが、やってみたい気持ちを後押しする効果があると言われています。
夫婦で楽しむ趣味の力
夫婦が共通の趣味を持つことは、関係の修復や深まりに大きく役立ちます。一緒に何かを体験することは、会話のきっかけになったり、お互いの感性や価値観を理解する助けになります(ここでいう「共感的理解」とは、相手の気持ちや考えを自分の視点だけでなく、相手の立場に立って理解しようとすることです)。
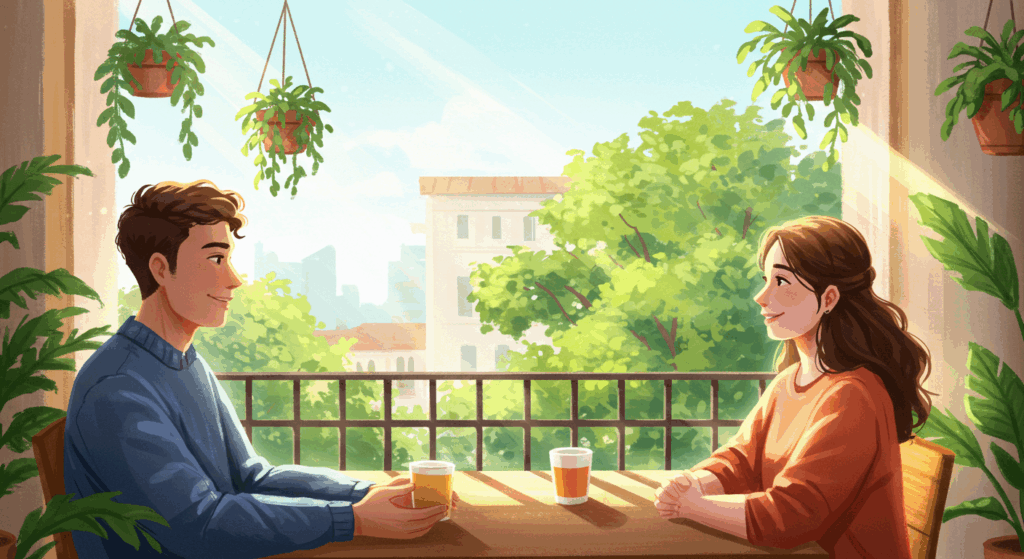
また、料理や旅行、陶芸、ハイキングなど、ふたりで協力しながら行う趣味は、「チーム」としてのつながりを強めてくれます。ウォーキングや軽い運動など、体を動かしながら会話もできる趣味は、心と体の両方に良い効果があります。
無趣味に対する支援と心がけ
パートナーが趣味を持っていないとき、周囲の支援には配慮と優しさが求められます。まずは「趣味をするための時間」を確保できるよう、家事や育児の分担を見直すことが必要です。
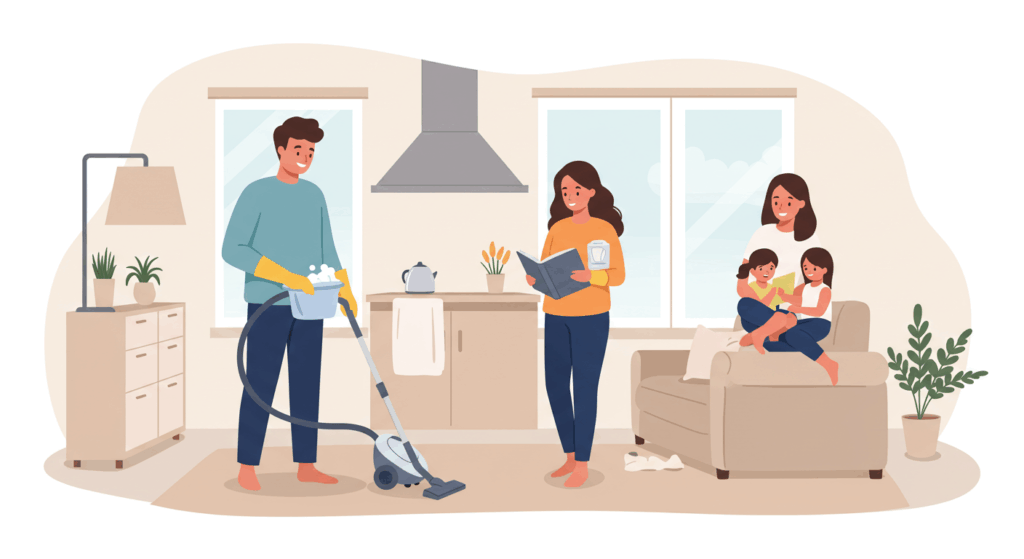
さらに、本人の興味や好奇心を否定せずにサポートする姿勢が大切です。支援する人が「こうすべき」と価値観を押し付けるのではなく、その人が自分で選んで決められるようにすることが理想です。どんな小さな一歩でも、温かく認めることが、自信やモチベーションを高めることにつながります。
無趣味をどうとらえるか
「無趣味」は性格の問題ではなく、生活環境や社会の仕組みによって生まれる「一時的な状態」(たとえば育児や介護で忙しい時期など)であることが多いのです。「趣味がある人が良い、ない人はダメ」といった単純な見方ではなく、さまざまな生き方や幸せのかたちがあるという理解が大切です。
大事なのは、趣味があるかどうかではなく、その人が「何かやってみたい」と思える環境を整えることです。こうした視点を持つことで、夫婦の関係がよくなり、ひいては社会全体の幸せにもつながる可能性があります。
まとめ
私の妻も無趣味だったので多趣味だった私には理解できず、いろいろ提案してみましたがどれも続かずイライラしたこともありました。ところが結婚生活20年目にして妻から山に登ってみたいと言われたときはビックリしました。妻が登山?全然想像ができなかったのです。

登山は私の趣味(写真・フライフィッシング)にも精通するので快諾しましたが、私はとても登山をする人の体系とは言えない完全なるメタボ体系。しかしこれは人生最大のチャンスと妻ファーストで道具を揃え挑んだ初登山は大成功。代償として私の膝は激痛。私も初めての登山でしたが楽しかったので続けるためにダイエットが必要です。これから何度も限界突破を求められる状況が増えるので。

妻の趣味が見つかり一緒に山に登るようになって凄い出来事がありました。何度もチャレンジして何度も挫折した禁煙。今は煙草を吸わなくなって半年が経過。まさかこの私が禁煙できるなんて本当に感謝です。
まだまだ登山初心者の私たちですが、老後に向けて体力低下防止になるし健康維持にもなるので後期高齢者になるまで妻と一緒に山を歩きたいと思います。
50代夫婦のライフスタイルと関係性の変更を楽しむ方法 – つまけん